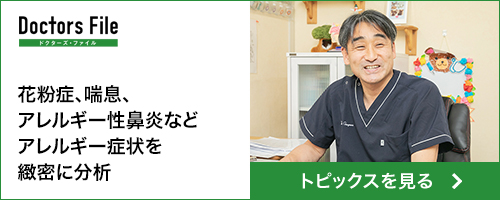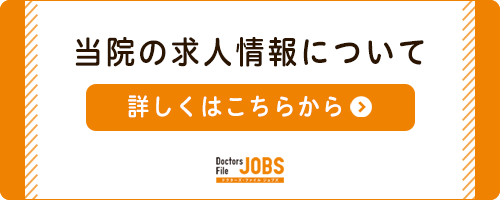-
アトピー性皮膚炎とは?
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎はアレルギー体質の人に痒みを伴う様々な湿疹が、慢性に経過したもの(乳児期で2か月以上、年長児で半年以上)です。
多くは左右対称に出現しますが、年齢によって好発部位が異なります。
乳児期は、顔や頭から徐々に全身に広がり、年齢が進むと首や膝の内側、大人になると上半身の湿疹が主体となる特徴があります。
子供の20%ぐらいが、アトピー性皮膚炎であるとされていますが、大部分は軽症です。
ただ、重症になると痒みによる夜間の睡眠障害により、家族共に日常生活に支障をきたします。見た目による精神的ストレスも生じますので、早めの治療をお勧めします。
-
アトピー性皮膚炎の原因について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能の破綻によって起こっています。
皮膚は、外敵の侵入の防御と体内の水分保持の役割がありまが、乾燥肌(ドライスキン)で皮膚のバリア機能が低下すると、様々な刺激を受けやすくなります。その刺激が原因となり、皮膚に痒みを生じ、皮膚を掻く。これにより更に皮膚のバリア機能を破綻させ、皮膚を悪化させるというのが一つの原因です。
もう一つは、皮膚の痒みそのものが原因であるといわれています。皮膚を掻くことで皮膚の炎症が起き、それにより神経から痒みを引き起こす物質が出て、更に掻くことで皮膚を悪化させてしまうということです。
ちなみに、43度以上の熱刺激が痒み刺激を引き起こすといわれています。体が温まると痒くなるのはそのためです。
また、最近のアトピー性皮膚炎の研究で「フィラグリン」という皮膚の外側の蛋白質の欠乏(乾燥肌になります)を引き起こす遺伝子異常と免疫システム(TH2サイトカイン)の異常も原因であるといわれています。
-
アトピー性皮膚炎の診断について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の診断をするために、その他のアレルギー疾患同様にアレルギー体質があるかどうかと、血液検査でアレルゲンの検索を行います。
ただ、慢性的に経過するのが定義なので、皮膚症状の経過を診て最終診断をすることになります。
小児のアトピー性皮膚炎ほとんどが1歳未満に発症するため、その時期に食物抗原の関与を診断することが重要です。
この時問題になるのは、アトピー性皮膚炎の食物抗原は、「即時型反応」より「遅滞型反応」が中心となるため、血液検査では陰性になることも多いことです。また、食物抗原が陽性の場合であっても、アトピー性皮膚炎への関与については関係ないこともあります。
その場合、軟膏療法で皮膚を良好な状態にします。その状態で、食物を摂取したときに皮膚の悪化が見られなければ、誘因抗原ではないと診断します。
逆に、軟膏療法で改善されない場合、推定される食品の除去を行います。それにより皮膚状態が改善され、再び摂取すると悪化がみられる場合、誘因抗原と診断することがあります。これを「食物除去負荷試験」といいます。
その他、アトピー性皮膚炎に特有の血液検査の「TARC」という皮膚の細胞から作られる物質を測る検査があります。
これは、現在の皮膚状態とその後の経過を客観的に数値化するのに役立ちます。しかし、乳児期では皮膚症状に関係なく高値を示すことがあります。
-
アトピー性皮膚炎の悪化因子について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の治療には、一人ひとりの悪化因子を見つけることが重要です。
また、これは一人の患者さんで複数存在しますし、年齢や環境、重症度の変化で変わっていきます。
アレルゲンとしては、乳児期に多いのは食物ですが、徐々にカビやダニなどの関与に変化します。その他ペットや花粉なども注意が必要です。その他の悪化因子としては、季節的には、春から秋までに多い紫外線や汗や汚れ。秋から冬までに多い乾燥のほか衣類や石鹸、シャンプー、皮膚の洗いすぎや皮膚を掻くことの機械的刺激もあります。
年長児以降は、ストレスでも悪化因子になることがあります。
最近、皮膚の悪化因子として皮膚の感染。その中でも黄色ブドウ球菌の関与の重要性が言われており、アトピー性皮膚炎では高率(80%以上)に培養陽性になるといわれています。
-
アトピー性皮膚炎の治療指針について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の治療は、三つの柱があります。
「スキンケア」
皮膚を清潔にして、保湿剤で乾燥を防ぎます
「薬物治療」
ステロイドの軟膏を中心に、痒み対策として抗アレルギー剤と抗ヒスタミン剤の内服を行います
「アレルゲンと悪化因子の除去です」
患者さんに応じたアレルゲンと悪化因子を特定して取り除きます
根底にあるアトピー体質や乾燥肌、敏感肌といった先天的なものを治すのは難しいので、この三つの治療を組み合わせて早期の無症状化を図ってほしいです。
治療の目的は、症状(特に痒み)のない、普通の生活は出来る状態までコントロールすることですが、最終的には、保湿剤のみで大丈夫な皮膚の状態にすることです。
-
アトピー性皮膚炎の薬物治療(外用薬)について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の炎症は、皮膚の表面に近いところで起こっていることがわかってきました。
その為、皮膚の表面からアプローチすることが重要です。
一時期、ステロイド薬の副作用が問題になりましたが、皮膚の炎症を抑えるにはステロイドが有効で、ガイドラインでも標準化治療となっています。
ただし、全身的な副作用はあまり考えなくてもよいのですが、局所の副作用(下記参照)を考えて、重症度や年齢(子供は皮膚から吸収されやすいため)、使用部位(顔、首、陰部は皮膚から吸収されやすく、特に目の周りは目の副作用を考えて特別な軟膏を使用など)を考え適切なランクのステロイド薬を塗布することが必要です。
【局所の副作用】
①長期使用すると皮膚が薄くなる
②毛細血管拡張
③毛が濃くなる
④ニキビができやすくなる
⑤リバウンド
最近、後述するステロイドの「プロアクティブ療法」を行うと副作用とリバウンドを起こしにくいということがわかってきました。
また、低年齢では使用できませんが免疫抑制剤の軟膏(プロトピック)があります。使用しても健常皮膚では吸入されにくいので、副作用は起きにくいのですが、刺激が強いのが難点です。
その他、抗炎症作用が軽微で接触性皮膚炎の副作用があり、外国では使われていないのですが、非ステロイド薬の軟膏(コンベックなど)を用いたり、感染の合併には抗生剤の軟膏(アクアチムなど)を使用します。
スキンケアの項に記載しますが、各種保湿剤もバリア機能回復とドライスキンのケアに必要です。
保湿剤を併用することで、ステロイド薬の使用量を減らすことも可能になります。
-
ステロイド軟膏療法とプロアクティブについて
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎が酷くなった時だけでなく、症状が消失した後も定期的にステロイド薬を塗布することを「プロアクティブ」といいます。これは、ステロイドの副作用とリバウンドを起こしにくいといわれています。
まず十分な量(これが大切です)のステロイド薬を連日塗布し、皮膚をきれいにします。
この時点ではまだ皮膚の完全な修復がなされていませんので中止せずステロイド薬塗布を継続します。
その後、徐々にステロイド薬を塗布する間隔を長くしていきます。
ただ、この減量は、患者さんの重症度や罹患期間、部位やステロイド薬の効果と副作用に応じて行います。
その後も、週に1~2回のステロイド薬の塗布を長期に維持すると皮膚から天然保湿因子が作られ、皮膚のバリア機能が回復されるといわれています。
最終的は、ステロイド薬を中止します。
「プロアクティブ」は副作用の軽減だけでなく、治療の成功例の報告も多くみられてきました。
最終目的の保湿剤のみで大丈夫な皮膚状態にするためには是非行ってほしい治療法です。
-
アトピー性皮膚炎の薬物治療(内服治療)について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎は、初診時や軟膏療法のみで痒みが酷くて眠れない場合や、日常生活に支障がある場合は、痒みを止めるために抗アレルギー薬(アレグラ、クラリチン、ザイザル、ザジテンなど)や抗ヒスタミン薬(タベジール、ペリアクチンなど)の内服薬の治療を行っています。
内服治療は、年齢や薬の種類によって眠気の副作用があります。
患者さんの効果と副作用を確認しながら治療を行います。
痒みが改善されれば、減量ないしは中止していきます。
-
アトピー性皮膚炎のスキンケアについて
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の「スキンケア」は、重症度に関わらず皮膚を清潔に保ち、乾燥を防ぐことが必要です。
毎日の入浴、シャワーで皮膚についたアレルゲンや細菌、汗や汚れなどを、石鹸をよく泡立てて手や柔らかい材質のガーゼなどで優しく洗い、すすぎ残しの無いようしっかり洗い流します。
痒みが酷い場合は、温度が高い(43度以上)と痒みを誘発するので温度と長湯に気を付けてください。
入浴直後(出来れば3分以内)は、皮膚が水分を含んでいますので、保湿剤をたっぷりと塗布してください。
保湿剤はヘパリン類似物質(ヒルドイド、ビーソフテンなど)や尿素製剤(ウレパール、ケラチナミンなど)、ワセリンなど処方しますが、市販のものでも自分の肌と相性のいいものを選んでください。
-
アトピー性皮膚炎の悪化因子対策について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の悪化因子は、病状や年齢、季節や環境因子によって変化しますので、常に分析してその対応を習慣づけてほしいと思っています。これは、かなり個人差があります。一般的な以下の対応などが必要です。
①石鹸やシャンプーはよく泡立てて洗う
手や柔らかい材質のガーゼ素材のものなどで洗う
すすぎ残しの無いようしっかり洗い流す
汚れや石鹸が残らないために、頭から下に向かって洗う
②風呂上りはすぐに(出来れば3分以内)に必要に応じて保湿剤を塗布する
③運動後などの汗、砂場や泥んこ遊びのあと、プールや海水浴の後は出来るだけすぐに洗い流す
④紫外線対策の為に直射日光を避ける対策とUVカットローションなどを使う
⑤衣類は刺激の少ない綿素材で、できるだけ柔らかい繊維のものを選ぶ
⑥温度変化が刺激になり痒みを増強させるので、エアコンの風が直接当たらないよう気を付け、こまめに着替えで調節する
-
アトピー性皮膚炎の重症度について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎は、湿疹の面積で重症度分類をします。
【軽 症】面積にかかわらず、軽度の皮疹のみ
【中等症】強い炎症がある皮疹が体表面の10%未満
【重 症】強い炎症のある皮疹が体表面の10~30%
【最重症】強い炎症はある皮疹が体表面の30%以上
乳幼児の8割以上は軽症だと言われています。
-
アトピー性皮膚炎の臨床的重症度と治療
▲目次へ戻る
実際には、外来受診の際に今までの治療での皮膚の評価を行います。
その後、治療をしたうえで、以下の治療方針を決定するのが現実的です。
【軽症】
スキンケアや増悪因子への対策を行い、弱めのステロイド軟膏と非ステロイド軟膏を適時使用する。
【中等症】
上記の治療が無効な場合や、最初から重症度が高い場合は、抗アレルギー薬と抗ヒスタミン薬の内服薬で痒みを止めると共に、ひとランク上のステロイド軟膏、免疫抑制剤の軟膏に変更します。アレルギー検査の検査結果を踏まえ、アレルゲン対策や悪化因子対策の見直しを行います。
【重症】
上記の治療で無効な場合は、漢方薬、抗真菌剤、抗生剤、紫外線療法、食物アレルギーの対する抗アレルギー剤(インタール)、ステロイド薬の内服、成人では免疫抑制剤の新薬(ネオラール)の内服や注射薬(デュピクセント)などを適時用います。
-
アトピー性皮膚炎の小児の特殊治療について
▲目次へ戻る
アトピー性皮膚炎の小児例の難治例に対して、学会レベルでは様々な治療が考案されてきました。
多くは追加治療ですが、ご紹介いたします。
アルカリイオン水や酸性水、超酸性水、海洋深層水の塗布、海水療法、イソジン外用療法です。
当院でも皮膚の感染対策として、イソジン療法を行うことがあります。
【方法】
①イソジン液を原液から4倍くらいに薄める
②柔らかいはけやガーゼで塗布する
③塗布後3分経って洗い流す
④その後患者さんに合った軟膏を塗布する
1日2回行い、2週間で効果判定をします。
今までの経験(500人以上)から、有効率は80%くらいです。
成人の手湿疹(別名主婦湿疹)にも(この場合はイソジンゲルを使用します)かなり効果的です。
おながわクリニック|おながわ小児科アレルギー科クリニック
〒819-0041 福岡県福岡市西区拾六町1-2-7
TEL. 092-885-7878|TEL&FAX 092-885-7885|アレルギー検査、食物アレルギー検査などお気軽にご相談ください。
電話はどちらでも繋がります
アレルギー疾患編 | アトピー性皮膚炎
「アトピー性皮膚炎」の目次
予防接種外来開始しました!
令和2年5月より開始
完全予約制で実施いたします
詳細はホームページ・院内掲示にてご案内予定です
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前一般診療受付8:30~11:50 診療8:40~12:00 |  |  |  |  |  |  |
| 健診予防接種外来
受 付14:00~14:30 専用外来14:00~15:00 |  |  |  |  |  |  |
| 午後一般診療
受付15:00~17:30 診療15:00~18:00 |  |  |  |  |  |  |
❖予防接種外来時間外も予防接種は実施可能です❖
おながわ小児科アレルギー科クリニック
〒819-0041 福岡県福岡市西区拾六町1-2-7